認知的不協和理論

人は自分の中で矛盾する認知(新し時事実)を突きつけられた時に不快感を感じます。
その矛盾した状態を解消するためには、これまで持っていた認知もしくは新しく入ってきた認知のどちらかを変化させることになります。
この理論を社会心理学用語で「認知的不協和」と言います。
この理論はアメリカの心理学者であるフェスティガーによって提唱されました。
ここでいう「認知」とは、人が何かを認識したり、新しいことを知る、感じた場合、それが何であるかを判断したり解釈したりする過程のことをいいます。
まずは身近な認知的不協和について紹介していきます。
・
・タバコ
喫煙者の大半は「タバコは体に良くない」ということを認知しています。
一方、「自分はタバコを吸っている」という認知もしており、「タバコは体に悪いが自分は吸っている」という矛盾が不協和を生じさせます。
この矛盾による不協和を解消や軽減するために認知を変化させることで、「心の協和」を保とうとします。
例えば、
「タバコを吸っても病気にならない人もいる」
「自分はタバコを吸うことでストレスを解消している」
などを新しく認知することで矛盾を正当化しようと考えてしまいます。
他にも「タバコを吸うのをやめる=禁煙する」という行動を取ることができれば、矛盾を解消することができます。
・
・ダイエット
ダイエットを始めるときに「今日からおやつを食べない」と決意したことはありませんか?
しかし、「おやつを食べることが習慣になっている人」や「甘いものが好きな人」にとっては、誘惑に我慢ができずに、ついつい手が出てしまいます。
このときも「おやつは食べない」という認知と「食べてはいけないのに食べてしまう」という認知により不協和が生じてしまいます。
この場合、
「少しぐらいなら大丈夫」
「ダイエットは明日から始めよう」
「今日を頑張った自分へのご褒美」
など、新しい認知をすることで「おやつを食べない」という認知に対しての不協和を軽減しようとしてしまいがちです。
・
・仕事
どんな仕事でも人と関わっている限り認知的不協和を感じているかもしれません。
例えば、先輩から
「今週中に今日の案件、データをまとめて報告してね」
と言われたとします。
あなたは
「わかりました」
と返事をしましたが、いざ仕事に取り掛かると思っている以上に難しく、
締め切り日までの時間が段々となくなってきます。
そうなると「今週中にデータを報告しなければいけない」という認知と「時間が足りないので間に合わない」という認知により不協和が生じて、ストレスがたまることでしょう。
締め切りまでに報告ができれば解消するかもしれませんが、作業中は
「締め切りまでの日数が短すぎる」
「先輩が手伝ってくれないから」
「自分のレベルでは難しい」
といった新しい認知をすることでストレスの低減をしようとします。
・
タバコ、ダイエット、仕事を例にしましたが、「認知的不協和」をイメージすることができたでしょうか?
例を見ても分かるように、認知的不協和とは、「矛盾が生じたときに発生するストレス」であり、解消や低減するためには「理由をつけて言い訳をする」と言えるのではないでしょうか。
この「認知的不協和を解消、低減する」ということは様々な場面で活用することができますので、紹介していきます。
・ビジネスでの活用
あなたは家電量販店で接客をしており、お客さんはテレビを購入するつもりですが、「最新モデル」か「値段が少し安い旧モデル」どちらにするかで悩んでいるとします。
この時、お客さんの中では「最新モデルは性能がいいけど高い」、「旧モデルは安いが最新ではない」という不協和が生じることで悩んでしまいます。
そこで、あなたが
「最新モデルは旧モデルよりも画質が良くて使い勝手もいいですよ。値段は少し高くなりますが、満足していただけると思います」
というようなアドバイスをしてみましょう。
そうすることで、お客さんは
「店員さんがここまで勧めるなら。」
「値段の差以上に満足できるなら」
というようにポジティブに考える可能性が高くなり、商品の購入に繋げることができるかもしれません。
アドバイスするときに「プラスになる情報」を伝えることが重要であり、
「最新モデルですが、旧モデルと値段以上の性能差はないですよ」や
「私が買うなら旧モデルでも十分かと思います」
など旧モデルに興味を持つような説明をするとお客さんはネガティブに捉えてしまうかもしれません。
どちらの場合もテレビを販売するということは変わりありませんが、「最新モデル」か「旧モデル」かで売上も変わることから、相手の認知をどのように変化させるかが重要となります。
ただし、相手の好感を得るための「嘘」や「話しの盛り過ぎ」には注意が必要です。
・子育てでの活用
小さいお子様がいる場合、子どもながらに様々な認知的不協和を生じていることがあります。
例えば、子どもの前でお酒を飲んでいると「なんでパパだけ?」や「大人だけずるい」など「自分は飲めない」という認知との矛盾からストレスを感じてしまいます。
このときに「大人だからいいの」など適当に答えてしまうと、「なんで大人だからいいの?」という新たな認知により、余計に疑念を与えることとなりストレスを感じるかもしれません。
「なぜ大人だけお酒を飲んでいいのか」ということをきちんと説明することができれば、子どもは新しい認知として不協和を解消できるでしょう。ただし、ある程度理解できる年齢にならないと説明しても納得できないと思いますので、その時は「お酒の代わりにジュースを飲んでいいよ」など相手に合わせて対応することも必要です。
・
子どもが幼稚園から小学生くらいになると友達の服装が気になったり、自分の服が似合っているかなど服装などにもこだわりが出てきたりしますよね。
そして友達からの何気ない一言で認知的不協和が生じることがあります。
例えば、いつものように友達と遊んでいると友達から
「その服、○○ちゃんぽくないね。あまり似合ってない」
と言われたとします。友達は悪気もなく、言葉に深い意味はありません。
しかし、言われた子どもからすると
「この服は自分に似合っていない」という新しい認知から「もうこの服は着たくない」という感情になってしまいます。しかし親からは「その服、とても似合っている」と言われている場合などは不協和が生じるためストレスが溜まってしまいます。
親からすると「せっかく買った服なので着てほしい」という感情になるとは思いますが、無理に着させるのはやめてあげましょう。
新しい認知を与えるとすれば、
「家族でお出掛けするときに来てくれればいいよ」や
「違うお友達と遊ぶときに着ていけば?」
などと声を掛けてみましょう。子どものストレスを軽減できるかもしれません。
また「せっかく買ったのにもったいない」という親心に関しては、
「こどもに無理やり着せるのはかわいそう」や「気分が変わるかもしれない」などの新しい認知を
することで解消できるようにチャレンジしてみましょう。
弟や妹がいる場合は「下の子に着せればいいか」と思うことでも不協和を解消しやすくなります。
・
以上、「認知的不協和理論」について紹介しました。
実際に思い当たる経験のある人も多いのではないでしょうか?
認知的不協和をうまく活用すれば、ダイエットや子育てからビジネスに至るまで様々な場面で活かすことができます。
是非取り入れてみてください。

四季グループ代表
【事業概要】
●コンセプトカフェの経営
●WEB制作/サイト運営
●芸能人キャスティングPR動画制作
●イベント企画運営

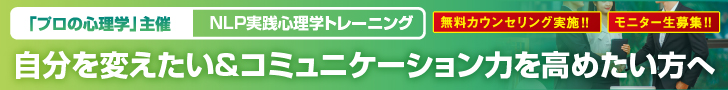

















この記事へのコメントはありません。